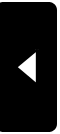2007年10月04日11:56
 拓殖大学学友会静岡県支部総会が、浜松市で行われた。この会の詳細は、小畑拓兄の記事に詳しく述べられているので、ここでは割愛する。
拓殖大学学友会静岡県支部総会が、浜松市で行われた。この会の詳細は、小畑拓兄の記事に詳しく述べられているので、ここでは割愛する。
ここでの話は旗の位置。
私の考えで、国旗を向かって右側に、校旗(学友会支部旗)を向かって左側に掲示した。
我が国の伝統儀礼からすれば、当然、向かって右手が上座となるから、当然其処に国旗が位置すべきと考え掲揚した。
後に某先輩から、「旗の位置が逆ではないか?」とご指摘を頂いた。
そこで少し調べてみた。
原則は国旗と他の団体旗を併揚するべきではない。しかし、止むを得ない場合は国旗を大きく、他の旗を小さく、国旗を上位(高位)に、他の旗を下位(低位)に掲揚するべきとされているそうだ。
ここで、上位が左か右かということが問題となるわけだが、国際儀礼では我が国とは逆で、向かって左が上位になるようだ。外国との関係の上からのみならず、国内でも公式行事などにこの考えが採用される場合が多い。
御真影(天皇・皇后両陛下の写真)を見ても、天皇陛下が向かって左、皇后陛下は向かって右となっている。雛人形でも男雛が向かって左・女雛は向かって右。結婚式の新郎新婦も同様だ。これらの事を国旗が向かって左である理由に上げる意見も多い。(我が国の伝統文化の中から理由を見出したいとする気持ちの現れか?)
我が国では、左翼(向かって右側)が上座とされていることは、周知のことだが、その理由は何か?
祭祀(政・まつりごと)を司る天皇が、日輪の方向(南)に向かって、日のいずる方向である東は天皇の左手の方向であり、日の没する方向である西は、天皇の右手の方向であり、日の没するよりも出る方が尊いという観点から、左側(向かって右側を上位とした。その為、天皇の左側(向かって右)に位置する左大臣が上席である。神道でも、神饌物の置く位置などはこれに倣っており、雛人形での男雛・女雛の配置も、本来は男が左(向かって右)で女が右(向かって左)だった。
どうして変わってしまったのか?
大正天皇即位大礼の際、西洋式に並んだのが切っ掛けだと、複数の文献で述べられていたが、大正天皇の時までは、天皇皇后両陛下揃って即位大礼に臨まれる事はなく、昭和天皇からだという記述も見られた。詳しい事情をご存知の方がいらっしゃれば教えて欲しい。
明治以降、洋装の場合は西洋式に並ぶ習慣が取り入れられるようになったそうだ。
西洋では何故向かって左が上位なのか?
「騎士が戦いの際、右手に剣を持ち、左手に婦人を抱えて守った」ことが理由という記述があった。
(情報不足のため、これに対する論評は、ここではしないこととする)
洋装であろうが、洋式であろうが、日本人が国内で行う行事は、我が国の、天然自然の理合に基いた儀礼に則って行うのが筋ではないかと、私は思う。
拓大学友会静岡県支部総会での旗の位置≫
カテゴリー │拓大
ここでの話は旗の位置。
私の考えで、国旗を向かって右側に、校旗(学友会支部旗)を向かって左側に掲示した。
我が国の伝統儀礼からすれば、当然、向かって右手が上座となるから、当然其処に国旗が位置すべきと考え掲揚した。
後に某先輩から、「旗の位置が逆ではないか?」とご指摘を頂いた。
そこで少し調べてみた。
原則は国旗と他の団体旗を併揚するべきではない。しかし、止むを得ない場合は国旗を大きく、他の旗を小さく、国旗を上位(高位)に、他の旗を下位(低位)に掲揚するべきとされているそうだ。
ここで、上位が左か右かということが問題となるわけだが、国際儀礼では我が国とは逆で、向かって左が上位になるようだ。外国との関係の上からのみならず、国内でも公式行事などにこの考えが採用される場合が多い。
御真影(天皇・皇后両陛下の写真)を見ても、天皇陛下が向かって左、皇后陛下は向かって右となっている。雛人形でも男雛が向かって左・女雛は向かって右。結婚式の新郎新婦も同様だ。これらの事を国旗が向かって左である理由に上げる意見も多い。(我が国の伝統文化の中から理由を見出したいとする気持ちの現れか?)
我が国では、左翼(向かって右側)が上座とされていることは、周知のことだが、その理由は何か?
祭祀(政・まつりごと)を司る天皇が、日輪の方向(南)に向かって、日のいずる方向である東は天皇の左手の方向であり、日の没する方向である西は、天皇の右手の方向であり、日の没するよりも出る方が尊いという観点から、左側(向かって右側を上位とした。その為、天皇の左側(向かって右)に位置する左大臣が上席である。神道でも、神饌物の置く位置などはこれに倣っており、雛人形での男雛・女雛の配置も、本来は男が左(向かって右)で女が右(向かって左)だった。
どうして変わってしまったのか?
大正天皇即位大礼の際、西洋式に並んだのが切っ掛けだと、複数の文献で述べられていたが、大正天皇の時までは、天皇皇后両陛下揃って即位大礼に臨まれる事はなく、昭和天皇からだという記述も見られた。詳しい事情をご存知の方がいらっしゃれば教えて欲しい。
明治以降、洋装の場合は西洋式に並ぶ習慣が取り入れられるようになったそうだ。
西洋では何故向かって左が上位なのか?
「騎士が戦いの際、右手に剣を持ち、左手に婦人を抱えて守った」ことが理由という記述があった。
(情報不足のため、これに対する論評は、ここではしないこととする)
洋装であろうが、洋式であろうが、日本人が国内で行う行事は、我が国の、天然自然の理合に基いた儀礼に則って行うのが筋ではないかと、私は思う。
参考にしたサイト
西野神社様・西野神社社務日記
面白半分・左右の内裏雛
天鳳堂様・おひなさまの豆知識
ちょっとぴんぼけ様・左右の理屈・左右ってどっち側?
福岡県国際交流センター様・掲揚儀礼
教えて!goo国旗の位置は右・左?
西野神社様・西野神社社務日記
面白半分・左右の内裏雛
天鳳堂様・おひなさまの豆知識
ちょっとぴんぼけ様・左右の理屈・左右ってどっち側?
福岡県国際交流センター様・掲揚儀礼
教えて!goo国旗の位置は右・左?