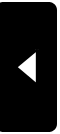2005年10月30日00:31
 古代より、世界中の至るところの国々で捕鯨は発達し一つの食文化としてその恩恵を受けながら、我々は生活をしてきたと言っても過言ではない。
古代より、世界中の至るところの国々で捕鯨は発達し一つの食文化としてその恩恵を受けながら、我々は生活をしてきたと言っても過言ではない。
しかし、捕鯨技術の発達と共に、その量と漁場は拡大し、やがては乱獲となり、気がついた時には絶滅の危機に直面するまでになってしまった。
また、それに追い討ちをかけたのが、1948年にIWC(国際捕鯨委員会)によって設けられた捕鯨規制。実はこれが、欠点だらけの大失策だったのだ。決められた期間中に、各国の船団が早い者勝ちに入乱れて獲りまくる捕鯨オリンピックと呼ばれたも。この結果、捕鯨の対象となったのは効率の良い大型のシロナガスクジラ、ナガスクジラ、ザトウクジラ等で、この種に捕鯨が集中したために、特この種が最も深刻な絶滅の危機を招く結果となった。
そして、これが引き金となり、・・・
鯨と鮪のこういう関係≫
カテゴリー │旨いもんの話
 古代より、世界中の至るところの国々で捕鯨は発達し一つの食文化としてその恩恵を受けながら、我々は生活をしてきたと言っても過言ではない。
古代より、世界中の至るところの国々で捕鯨は発達し一つの食文化としてその恩恵を受けながら、我々は生活をしてきたと言っても過言ではない。しかし、捕鯨技術の発達と共に、その量と漁場は拡大し、やがては乱獲となり、気がついた時には絶滅の危機に直面するまでになってしまった。
また、それに追い討ちをかけたのが、1948年にIWC(国際捕鯨委員会)によって設けられた捕鯨規制。実はこれが、欠点だらけの大失策だったのだ。決められた期間中に、各国の船団が早い者勝ちに入乱れて獲りまくる捕鯨オリンピックと呼ばれたも。この結果、捕鯨の対象となったのは効率の良い大型のシロナガスクジラ、ナガスクジラ、ザトウクジラ等で、この種に捕鯨が集中したために、特この種が最も深刻な絶滅の危機を招く結果となった。
そして、これが引き金となり、・・・
捕鯨禁止へと傾いていった。
IWCは、1962年にシロナガスクジラとナガスクジラの捕獲禁止を打ち出して、国別に枠を設ける方式へと変更し、その保護に早速乗り出した。
しかし、一方欧米では、自然保護の風潮が広がりつつあり、クジラは「平和的な動物」というイメージが定着する中、1972年、ストックホルムでの人間環境会議にて「商業捕鯨を10年間禁ズ」と決議され、さらに、政治的に力を持った反捕鯨勢力の攻勢はIWCにも及び、1982年、全ての商業捕鯨を1986年から凍結する「商業捕鯨モラトリアム」が採択されるに至った。
マグロ船の猟師から、「延縄の針にかかったマグロを、クジラが待っていて、針のついた頭だけ残して食べていく。」「漁獲されたマグロの胃に餌が見当たらない。」など、数々の報告が上がっている。
また、ミナミマグロは主にオキアミを食しており、増え過ぎた南氷洋のミンククジラもこのオキアミを主食にしている関係からか、近年、このオキアミが減少し、身痩せした『ガリ』と呼ばれるミナミマグロが多くなってきているばかりでなく、ミナミマグロの絶対量すら不足傾向にあり、漁獲制限も取り沙汰されている有様だ。
現在、IWC他によるクジラ資源の保護と調査により驚くべき事実と報告が寄せられている。それによると、かつて乱獲の対象となったシロナガスクジラ等の一部の大型種を除き、小型の種、特にミンククジラが異常繁殖して自然界の生態系まで変わり始めてしまっているというものだ。ミナミマグロを中心としたマグロの水揚げ量の激減からはじまり、近海・遠洋を含めた小魚類の減少など、鯨と同水域に生息するものとの因果関係に疑う余地は無いようである。
IWCでは、調査捕鯨の対象となっている「ミンククジラ」は、南氷洋だけでも現在、約76万頭以上もの数がいるとし、「年間2000頭の捕鯨が可能」と算出している。
現在、日本が調査を目的に捕獲しているのは年間540頭余り。正しい調査と保護のもとに、まずはミンククジラの捕鯨を再開しなければ、ますます地球の生態系は犯されていく。つまり、美味しい天然マグロが食べられなくなるということだ。
IWCは、1962年にシロナガスクジラとナガスクジラの捕獲禁止を打ち出して、国別に枠を設ける方式へと変更し、その保護に早速乗り出した。
しかし、一方欧米では、自然保護の風潮が広がりつつあり、クジラは「平和的な動物」というイメージが定着する中、1972年、ストックホルムでの人間環境会議にて「商業捕鯨を10年間禁ズ」と決議され、さらに、政治的に力を持った反捕鯨勢力の攻勢はIWCにも及び、1982年、全ての商業捕鯨を1986年から凍結する「商業捕鯨モラトリアム」が採択されるに至った。
マグロ船の猟師から、「延縄の針にかかったマグロを、クジラが待っていて、針のついた頭だけ残して食べていく。」「漁獲されたマグロの胃に餌が見当たらない。」など、数々の報告が上がっている。
また、ミナミマグロは主にオキアミを食しており、増え過ぎた南氷洋のミンククジラもこのオキアミを主食にしている関係からか、近年、このオキアミが減少し、身痩せした『ガリ』と呼ばれるミナミマグロが多くなってきているばかりでなく、ミナミマグロの絶対量すら不足傾向にあり、漁獲制限も取り沙汰されている有様だ。
現在、IWC他によるクジラ資源の保護と調査により驚くべき事実と報告が寄せられている。それによると、かつて乱獲の対象となったシロナガスクジラ等の一部の大型種を除き、小型の種、特にミンククジラが異常繁殖して自然界の生態系まで変わり始めてしまっているというものだ。ミナミマグロを中心としたマグロの水揚げ量の激減からはじまり、近海・遠洋を含めた小魚類の減少など、鯨と同水域に生息するものとの因果関係に疑う余地は無いようである。
IWCでは、調査捕鯨の対象となっている「ミンククジラ」は、南氷洋だけでも現在、約76万頭以上もの数がいるとし、「年間2000頭の捕鯨が可能」と算出している。
現在、日本が調査を目的に捕獲しているのは年間540頭余り。正しい調査と保護のもとに、まずはミンククジラの捕鯨を再開しなければ、ますます地球の生態系は犯されていく。つまり、美味しい天然マグロが食べられなくなるということだ。